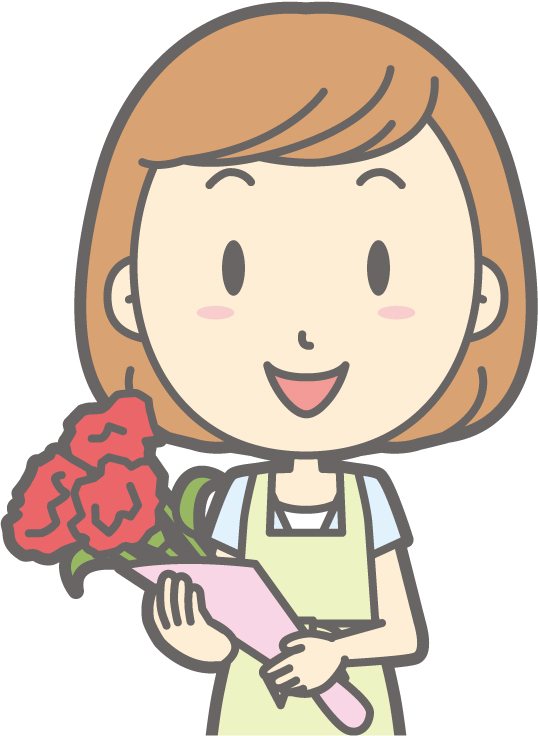電化製品を購入するときにエアコンや暖房器具など
何畳用という表示がされていますよね。
最近のご家庭では畳の部屋ではなく、
フローリングが大半を占めているのではないでしょうか?
そういう時、この部屋って何畳なの?と思ったことありませんか?
そんな時にお役に立つ、畳一畳の大きさと
関東と関西で違う畳の謎についてまとめました。
一畳ってどれくらい?
一言に「一畳」と言っても地方によってその大きさは微妙に違ってきます。
主に関東地方では、江戸間というサイズです。
一畳は 88.0cm x 176.0cm(1.54平米)
6帖間は 261cm × 352cm
主に東海地方では、中京間というサイズです。
一畳は 91.0cm x 182.0cm(1.65平米)
6帖間は 273cm × 364cm
主に関西地方では、京間というサイズです。
一畳は 95.5cm x 191.0cm(1.82平米)
6帖間は 286cm × 382cm
公団住宅などでは、団地間というサイズです。
一畳は 85.0cm x 170.0cm(1.44平米)
6帖間は 255cm × 340cm
一畳の長さの比率は縦横1:2となっていて、並べると正方形になります。
江戸間と京間を比較すると、縦25cm 横30cmの差があります。
これは畳約一畳分に相当します。こんなにも差があるんですね!
ちなみに不動産屋さんの広告で、○畳と表示されているのは、
一畳 90cm x 180cm(1.62平米)で計算するようです。
部屋の大きさが何畳かわからない時は、
平米数を1.62で割るとおおよその畳数が計算できます。
地方によって大きさが違うのは何故?
では、何故地方によって一畳の大きさが違ってくるのでしょう?
それは家の建て方に違いがありました。
古くから関西では、家を建てる時に畳の大きさに合わせて家を建てていたようです。
畳の大きさが変わらなければ、建てられる家の部屋の大きさも変わらないことになります。
しかし、関東では家を建ててから畳をはめ込むような作り方をしていたため、
柱の出っ張った部分を回避して、畳を敷かなくてはなりません。
そうするとどうしても柱の分だけ、少し小さな畳のサイズになってしまいます。
こうした家の建て方の違いから、一畳の大きさが変わってしまったようです。
ちなみに関西地方は畳割り、関東地方は柱割りと呼ばれるそうです。
少しはお役に立ちましたでしょうか?
最後までお読み頂きありがとうございました。