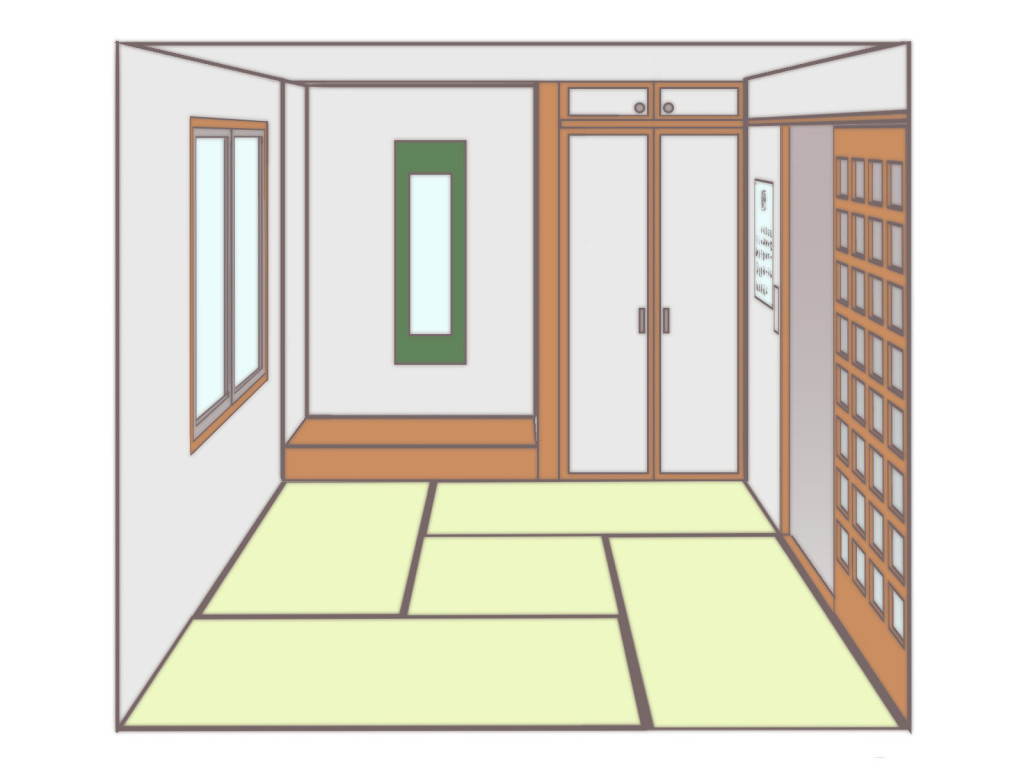皆さん”ほおずき市”という言葉を耳にしたことはあるでしょうか?
夏になるとテレビでも紹介される夏の風物詩の”ほおずき市”ですが、
今回はその”ほおずき市”の由来と楽しみ方について調べてみました!
ほおずきってなに?ほおずき市の由来は?
昭和世代の方はお馴染みだと思いますが、
最近ではあまり見かけなくなってしまったいましたね。
ほおずき市の”ほおずき”とは、
ナス科の多年草で夏になると黄白色の花を咲かせます。
その後に提灯のような袋の中にミニトマトのような果実ができます。
日本では主に観賞用として栽培されてきましたが、
ヨーロッパでは古くから食用のほおずきの栽培がされ、
フルーツのような甘酸っぱい独特の味わいが人気だそうです。
日本でも近年は食用として栽培がされるようになったようで
近い将来皆さんの食卓でもお馴染みの食材となるかもしれませんね!
それでは、ほおずき市の由来についてですが、
観音様のご縁日と深く関係があるそうです。
毎月18日が観音様のご縁日と言われています。
このご縁日とは別に室町時代以降に功徳日(くどくび)と言われる
縁日が新たに設けられたそうです。
功徳日に参拝すると100日分、1000日分の功徳(ご利益)が
得られると伝えられているそうです。
そんな功徳日の中でも、7月10日は四万六千日(しまんろくせんにち)
と言って46000日、年に換算するとなんと約126年分もの
ご利益があるとされ古くから信仰されているようです。
その四万六千日のご縁日にちなんで開かれるのが、”ほおずき市”ということです。
ほおずきは薬草としての評判があり、
ほおずきを水で鵜呑みにすると、大人は”しゃく”を切り、
子どもは”虫の気”を去ると言われていたそうです。
“しゃく”というのは胸やお腹が急に痙攣を起こし痛むこと、
“虫の気”というのは子供が寄生虫などによって
お腹が痛くなることを言うそうで、
ほおずきはそれらを治してくれる大事なお薬だったということですね。
ほおずき市の楽しみ方
ほおずき市というと浅草寺が有名ですね。
他にも芝にある愛宕神社(実はこちらがほおずき市の元祖です!)や
六本木にある朝日神社などでも行われいています。
ほおずき市に行くと風鈴の音色がとても風情を感じていいですね。
鉢植えのほおずきに風鈴がセットになって売っていますので、
一夏の思い出に購入して育ててみるのはもちろん、
ほおずきは見るだけではなく遊べちゃうんです。
ほおづきの実の中身を楊枝などを使って破かないように
優しくキレイに取り出して、空になったら空気を送り込んであげると
笛になります、音を出すにはちょっとコツが入りますが、
お子さんがいらっしゃるご家庭でしたら、
一緒に作って楽しめるんじゃないでしょうか?
小さい頃の思い出って大人になってからもずうっと残りますからね、
この夏はそんな昭和的な遊びを一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか?
最後までお読み頂きありがとうございました。